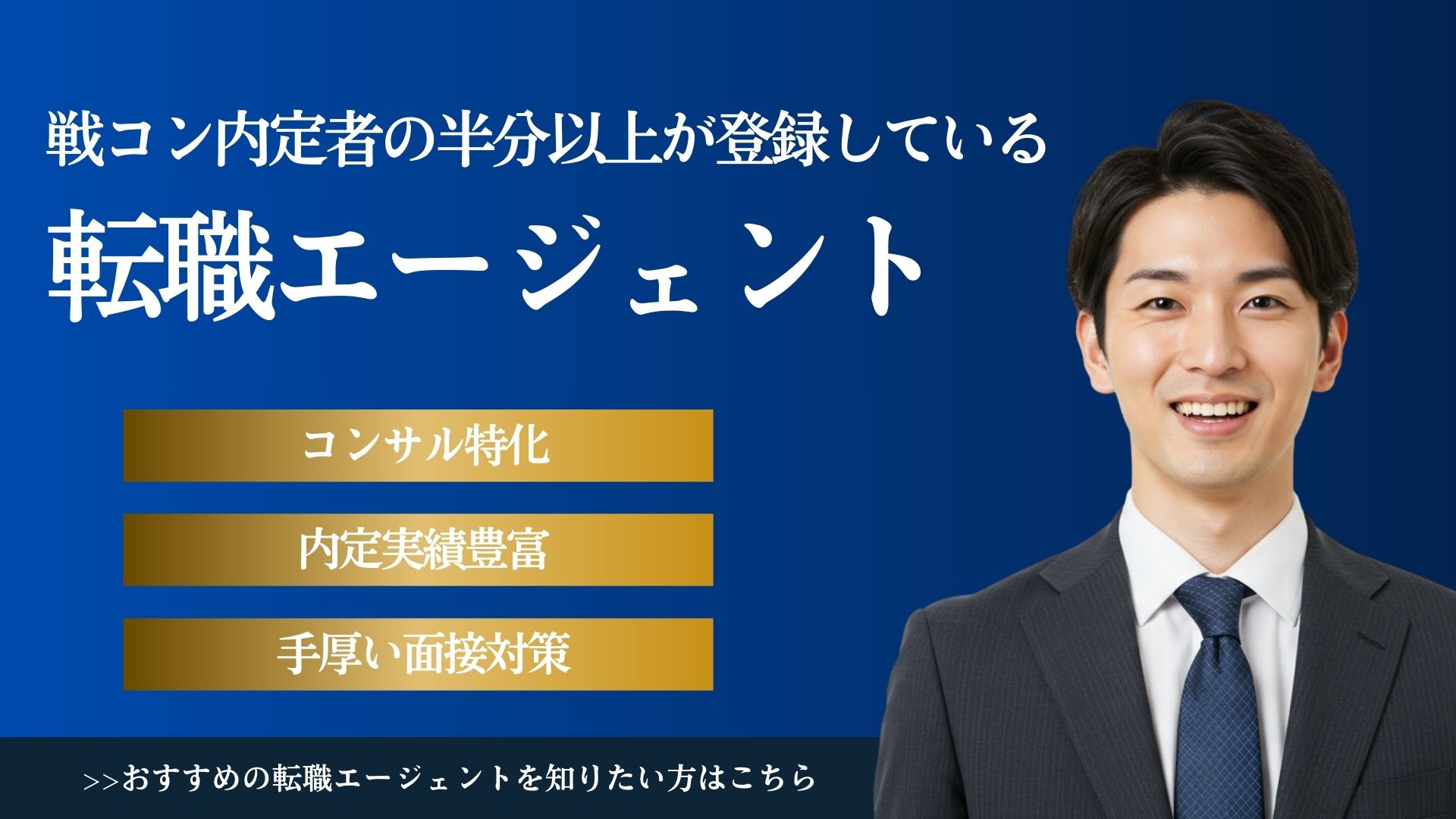たった3カ月で
MBB突破レベルのケース面接力が身につく
ケース面接対策塾
- 内定率77%のケース面接対策塾(平均内定率は1%以下)
- MBB出身者によるマンツーマンレッスン
- 転職による平均年収300万円UP
- 独自カリキュラムを使った効率的な学習
戦略コンサルティングファームへの転職を目指す方にとって、エージェント選びは合否を左右する重要です。特にマッキンゼーやBCG、ベインなどTop Tierと呼ばれるファームに行きたいと考えている方にとっては、案件紹介だけではなくケース面接の過去問や対策ノウハウ、業界の内情をどれだけ手厚くサポートしてもらえるかで合否が大きく変わってきます。
本記事では、戦略コンサル転職に強みをもつ転職エージェントを厳選してご紹介します。また、エージェントを利用するメリットや選び方、利用時の注意点など、戦略コンサル転職で押さえておくべきポイントを徹底解説します。
転職エージェントの利用すべきかどうかについてはいろいろな意見がありますが、使うことによりメリットはかなり大きいと考えています。コンサル業界の内定獲得へ少しでも近づくために、ぜひ参考にしてください。
外資戦略を目指すならまず話を聞くべき転職エージェント
▼このボタンから簡単30秒で登録▼
- 1位: MyVision 《未経験からMBB多数》
- 2位: アクシスコンサルティング《転職実績が圧倒的》
- 3位: コンコード《過去問多数保有》
- なぜ戦コン転職においてエージェント選びが重要か
- 戦略コンサル転職でのエージェントの選び方
- 外資戦略コンサルにいくならおすすめの転職エージェント
- MyVision (マイビジョン)
- アクシスコンサルティング
- コンコードエグゼクティブグループ
- ワンキャリアプラス (ONE CAREER PLUS)
- ビズリーチ (BizReach)
- リメディ (Remedy)
- コンサルネクスト.jp
- ムービン (movin’)
- ハイパフォキャリア
- CDBエージェント
- MWH HR Products (MHRP)
- テックゲートエキスパート
- コトラ (KOTORA)
- ASSIGN AGENT
- JAC Recruitment
- doda X
- リクルートダイレクトスカウト
- エグゼクティブリンク
- アンテロープ (Antelope)
- クライス&カンパニー
- ランスタッド
- FlowGroup (フローグループ)
- タイグロンパートナーズ
- リネアコンサルティング
- キャリアインキュベーション
- フォルトナ (FORTNA)
- ヤマトヒューマンキャピタル
- パソナキャリア
- LHH転職エージェント
- エンワールド
- 転職エージェントを利用するメリット
- 転職エージェントとリファラル・直接応募の比較
- 転職を成功させるためのエージェントの活用方法
- 転職エージェント利用の流れ
- エージェント利用で注意すべきこと
- 戦略コンサル業界の転職でよくある質問
- 3カ月の徹底攻略で戦略コンサルに内定したいならStrategy Academyがおすすめ
なぜ戦コン転職においてエージェント選びが重要か
戦略コンサルへの転職を検討する方にとって、転職エージェントの選択は合否に直結するといっても過言ではありません。マッキンゼーやBCG、ベインなどトップファームの採用フローは、通常の一般企業とは大きく異なりケース面接やフェルミ推定といった特殊な選考が行われるのはもちろん、応募から内定までのスピードが速い場合も多く、正しい対策や情報がないまま挑むと、あっという間に不合格になってしまう可能性があります。
さらに、戦略コンサルは一度落ちると再受験まで半年〜1年は間を空けないといけないケースが大半です。準備不足のまま突撃してしまい「もう少し対策してから受ければよかった……」と後悔する例も少なくありません。そのため、
- 過去問や面接のリアルな傾向を豊富に持っている
- 書類添削やケース面接の模擬練習ができる体制がある
- 各ファームの人事部門やパートナーとの太いパイプがある
等のメリットがあり、それぞれの相性によって変わってきます。
- MBBを含むトップファームへの転職に強い
- 外資戦略ファーム出身のカウンセラーによる指導が可能
- 未経験からの転職実績が豊富
![]() 【登録はこちら!】
【登録はこちら!】
▼このボタンから簡単30秒で登録▼
戦略コンサル転職でのエージェントの選び方
戦略コンサルファームへの転職を成功させるためには、どのエージェントと組むかが大きなポイントになります。外資系や総合系、ブティックファームなど、さまざまなタイプのコンサルティングファームがある一方で、それぞれの領域に強みを持つエージェントも多数存在します。ここでは、戦略コンサル転職を見据えた際にエージェントを選ぶ際の基準や、押さえておきたい注意点を具体的に解説します。
希望の業界・職種の求人数
戦略コンサルの求人取り扱い実績
最初に確認しておきたいのが、希望する業界・領域の求人がそのエージェントにどれだけあるかです。たとえば、MBB等のトップファームを軸に考えているのか、日系戦略ファームやブティック系も視野に入れるのかによって、自分に合うエージェントは変わってきます。
- 外資系戦略コンサルが多数取り扱われているか
- 日系大手コンサルファームの非公開求人がどれだけあるか
- ブティックファームへの転職実績が多いか
こうした要素を見比べることで、エージェントの得意領域を把握しましょう。
非公開求人の有無
特にブティックファームの求人は、社内事情や機密保持の観点から“非公開”になっているケースも多いです。非公開求人は、企業の経営戦略や組織再編のタイミングと連動して急に発生することがあるため、エージェントの情報力が物を言います。情報感度の高いエージェントであればその分だけ合格率を高めるチャンスが広がります。
コンサル業界の専門性の有無
コンサルタント出身のキャリアアドバイザー
戦略コンサル特有の選考フローや面接形式(ケース面接、フェルミ推定など)を熟知しているかどうかで、対策の質が大きく左右されます。特に担当アドバイザーが元コンサル出身であれば、
- 選考対策でのポイント(書類・面接)
- 面接官が重視する“思考プロセス”
- 案件・プロジェクトのリアルな内容
など、実務に基づいたアドバイスを得られる可能性が高いです。自分の希望先や志望動機をヒアリングしてもらう際、ロジカルに掘り下げてもらえるのは心強いメリットとなります。
コンサル業界との太いパイプと実績
エージェントが「このファームの人事部と長年つながりがある」「このパートナーと直接話せる関係性を持っている」などの場合、選考のスピード感や質問へのレスポンスがよりスムーズになります。特にマッキンゼーやBCGなど外資戦略ファームでは、採用担当と候補者との仲介役としてエージェントが活躍する場面が多く、しっかりとしたコネクションを持つエージェントを選ぶことが合否に直結するケースもあります。
面接対策や職務経歴書添削サポート
戦略コンサルならではの書類作成サポート
一般企業向けの職務経歴書添削と、戦略コンサル向けのそれは内容が大きく異なります。具体的な数値目標や成果、リーダーシップの発揮、問題解決のプロセスなど、コンサル特有の評価項目をクリアに示すことが重要です。
エージェントの中には「コンサル業界に精通した書類選考のスペシャリスト」が在籍しているところもあります。自分の経歴をどう“コンサル的”に表現し、かつロジカルな読みやすい文章に仕上げるか、密にサポートしてもらえるかをチェックしましょう。
ケース面接・ビヘイビア面接の模擬練習
戦略コンサルの面接で最も重要視されるのがケース面接です。この面接は暗記だけでなく、実際の“対話形式”で練習を重ねないと本番でミスが出やすいのが特徴。
- 実践的な模擬面接をしてもらえるか
- 「構造化が甘い」「優先度のつけ方が不十分」といったポイントを具体的に指摘してくれるか
- ビヘイビア面接(一般質問)に対してもコンサル視点でアドバイスが得られるか
ここまでのサポートができるエージェントはほぼいないですが、運よく良い担当者に当たればしっかりと対策をしてもらえる可能性もあります。
キャリアカウンセラーの質・相性
経験豊富なカウンセラーを選ぶ
エージェント企業の評判が良くても、実際に担当してくれるキャリアカウンセラーの経験や実績が低いと、満足なサポートが得られない場合があります。特に戦略コンサルは高い専門性が要求されるため、担当カウンセラーがコンサル転職を多数扱った経験を持っているかをチェックしましょう。
- 過去にどれだけの戦略コンサル転職成功事例をサポートしたか
- 応募者の年齢層や経歴が自分に近い人が多いか
- どのレベル(MBB、総合系、ブティック系)のファームへの内定獲得支援実績があるか
転職ペースを尊重してくれる姿勢
転職エージェントは成果報酬型ビジネスのため、「一刻も早く内定を取って欲しい」と急かす担当者もいます。しかし戦略コンサルの場合、ケース面接で一度落ちると再応募まで半年~1年は間隔を空けなければならないケースが一般的で、準備不足での特攻は危険度が高いです。
「まだケース対策が仕上がっていないから選考を後ろ倒しにしたい」「志望度の低い企業から練習を重ねたい」といった要望に対して、しっかり理解を示し、柔軟にスケジュールを調整してくれるカウンセラーを選ぶことが重要です。
実際の利用者の声や口コミを参考にする
インターネット上には、転職エージェント利用者の口コミや体験談が多数存在します。
- 「キャリアカウンセラーが親身で、書類添削が的確だった」
- 「あまり戦略コンサルに詳しくなく、納得いくサポートが得られなかった」
など、サービスの実際の質を知るうえで有益なヒントになる場合があります。
また、エージェントによっては公式サイトやカウンセラーから「どのファームに何人の内定実績があるか」を教えてもらえることも。たとえば「昨年度だけでMBBに××人、総合系に○○人の内定者を輩出」などのデータがあれば、そのエージェントの得意領域が見えてきます。過去に自分と似た年齢・スキル・業界出身の方が合格した実例を持っているかどうかも重要なチェックポイントです。
複数のエージェントを併用し、最適な担当を見つける
戦略コンサルへの転職を目指す際、最初から1社のエージェントだけに頼らず、複数エージェントに登録して比較するのが一般的です。その理由としては、
- 担当者との相性: 一社で合わないと感じたら他社に切り替えやすい
- 求人のカバー範囲: エージェントによって保有する案件や得意分野が異なる
- サービスの比較検討: 面接対策や書類添削の質がどこまで手厚いかを見比べられる
ただし、登録しすぎると管理が大変になるので、2~3社を目安に選ぶと良いでしょう。実際の面談を通じて担当者の対応や専門性を確認し、よりフィット感のあるところをメインで利用するとスムーズに進められます。
外資戦略コンサルにいくならおすすめの転職エージェント
MyVision (マイビジョン)
株式会社MyVisionが提供するMyVisionは、コンサル特化型転職エージェントで、外資系戦略コンサル求人に強みがあります。トップ戦略ファーム出身者が在籍し、独自の面接対策資料や模擬面接で徹底的にサポート。未経験者でも豊富な内定成功事例があり、幅広いコンサル求人を網羅しているので戦略ファーム志望者にもおすすめです。
| 運営会社 | 株式会社MyVision |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 外資系戦略コンサル求人に強く、内定成功実績が豊富 |
| 公式サイト | my-vision.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 専門家の徹底サポートで、幅広い求人にアクセス可能 |
| デメリット | 非公開求人中心で情報が見えにくく、地方求人は少なめ |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 外資系戦略コンサルを目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~30代半ば |
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティング株式会社が運営するAXIS Consultingは、20年以上の実績を持つコンサル特化型転職エージェントです。戦略系からIT、経営企画まであらゆるコンサル求人を網羅し、元コンサルタントが多数在籍。書類作成や面接対策、ケース面接の指導など、業界ならではのポイントを押さえたサポートが受けられます。
| 運営会社 | アクシスコンサルティング株式会社 |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 20年以上の実績、元コンサル出身者が多数在籍 |
| 公式サイト | axc.ne.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 企業内部情報に基づく具体的な支援が受けられる |
| デメリット | 担当者との相性により対応がばらつく可能性がある |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 外資系戦略コンサルを目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~40代 |
コンコードエグゼクティブグループ
株式会社コンコードエグゼクティブグループは、ハイクラス特化型の転職エージェントとして、特にIT・金融・コンサル業界に強みを持ちます。年収800万円~2000万円超の非公開求人を多数保有し、各業界の出身者が担当することで企業のリアルな内部情報に基づいたアドバイスが得られます。管理職クラスへの転職を目指す方に最適です。
| 運営会社 | 株式会社コンコードエグゼクティブグループ |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 年収800万~2000万円超の案件が豊富、エグゼクティブ層の転職に強み |
| 公式サイト | concord-group.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 独占非公開求人多数、ハイクラス転職支援に強み、企業の内部情報に詳しい |
| デメリット | ハイクラス層向けのため、経験やスキルが一定以上ないと厳しい |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | エグゼクティブ層や高年収を狙う方、戦略コンサル・投資銀行・PEファンド志望者 |
| 対象年齢 | 30代~50代 |
ワンキャリアプラス (ONE CAREER PLUS)
株式会社ワンキャリアが運営するワンキャリアプラスは、中途向けの転職DB型サイトです。登録後は各企業の選考情報やケース面接過去問など、膨大なデータベースを活用して、戦略コンサルを含むハイクラス求人のリアルな情報が得られます。また登録すると担当者がつき、未経験者にも手厚いサポートを提供しております。非公開求人も多数あるので戦略ファームを志望する方もおすすめです。
また、面接の過去問や聞かれた質問をここで見ることもできますので、受ける方は必ずチェックしておきましょう。
| 運営会社 | 株式会社ワンキャリア |
|---|---|
| タイプ | 総合型(情報プラットフォーム系)・コンサル含むハイクラス転職サイト |
| 主な特徴 | 選考情報・ケース面接過去問が充実。企業OBの口コミや選考情報も提供。 |
| 公式サイト | plus.onecareer.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 記載なし |
| メリット | 豊富な選考対策情報を無料で取得可能。幅広いキャリア情報が比較できる。 |
| デメリット | 専任エージェントの伴走支援が限定的。応募や日程調整は自己責任。 |
| 対応地域 | 全国(オンライン利用) |
| こんな人におすすめ | 業界研究から始めたい方、幅広い求人を比較したい方 |
| 対象年齢 | 20代~30代前半 |
ビズリーチ (BizReach)
ビズリーチは、ハイクラス向け転職サイトで、年収500万円以上の求人が豊富です。スカウト型システムにより、登録するだけで企業から直接オファーが届く仕組みを採用。特に外資系企業やグローバル案件に強みがあり、各社の特別採用ルート等の情報も得られるため登録しておくことをおすすめします。
| 運営会社 | 株式会社ビズリーチ |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス向け転職サイト(スカウト型) |
| 主な特徴 | 年収1,000万円超求人が豊富。直接スカウトが届く仕組み。 |
| 公式サイト | bizreach.co.jp |
| 公開求人数 | 約147,967件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | なし |
| メリット | 高待遇求人が多く、直接スカウトが届くため効率的。 |
| デメリット | 一定の年収・経験が必要。無料会員は機能制限あり。 |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 自身の市場価値を試したい方、複数オファーを期待する方 |
| 対象年齢 | 30代~50代(若手も高スキルなら可) |
リメディ (Remedy)
株式会社リメディが提供するリメディは、コンサル特化型の転職エージェントです。M&A仲介やスタートアップ、成長中のベンチャー求人など、他エージェントでは出会えない限定非公開求人を保有。コンサル出身の担当者が徹底した選考対策とキャリア設計の相談を行い、戦略コンサルへの転職支援に実績があります。
| 運営会社 | 株式会社リメディ |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型・ハイクラス転職エージェント |
| 主な特徴 | 戦略コンサルを中心に、M&Aやメガベンチャーの厳選求人を保有。 |
| 公式サイト | remedy-tokyo.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | あり |
| メリット | コンサル出身者による選考対策が充実。限定求人が豊富。 |
| デメリット | ハイクラス中心のため求められるスキル水準が高め。 |
| 対応地域 | 全国(主に東京中心) |
| こんな人におすすめ | 戦略コンサルやM&A、ベンチャー志望者。長期的なキャリア相談もしたい方。 |
| 対象年齢 | 20代後半~40代 |
コンサルネクスト.jp
株式会社みらいワークスが運営するコンサルネクスト.jpは、コンサル特化型転職エージェントです。中堅・中小のコンサルファーム求人に強く、未経験者でも安心して利用できる支援体制を整えています。第二新卒~30代前半が主な対象で、企業ごとのカルチャーや選考のリアルな情報を提供し、転職成功への確実なサポートを実施しています。
| 運営会社 | 株式会社みらいワークス |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型(中堅・中小ファーム向け) |
| 主な特徴 | 中小規模ファーム求人に強く、未経験者歓迎の支援が充実 |
| 公式サイト | consulnext.mirai-works.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 実践的な対策と企業カルチャー情報が得られる |
| デメリット | 大手求人は少なめ、知名度が低い可能性 |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 中小ファームから経験を積みたい未経験者 |
| 対象年齢 | 20代~30代前半 |
ムービン (movin’)
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリアが運営するムービンは、日本初のコンサル特化エージェントとして29年の実績を誇ります。国内ほぼ全てのコンサルファームの求人情報を網羅し、書類添削やケース面接対策など、未経験からでも実績を上げられるよう丁寧なサポートを提供。若手から中堅層を中心に、内定成功率の高さが評価されています。
| 運営会社 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 国内全コンサル求人網、29年の実績、手厚いサポート |
| 公式サイト | movin.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 長期実績と豊富な求人、丁寧な面接対策が魅力 |
| デメリット | 40代以上は求人が限定的な場合がある |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 20~30代でコンサル未経験から挑戦したい方 |
| 対象年齢 | おおむね25~35歳 |
ハイパフォキャリア
INTLOOP株式会社が運営するハイパフォキャリアは、コンサル業界専門で20年以上の実績を誇る老舗エージェントです。38,000人以上の転職支援実績があり、企業の詳細な求人情報と、現役コンサル出身の担当者による手厚いサポートが特徴。年収300万円以上のアップ事例が多数報告されており、ミドル層からエグゼクティブ層まで幅広く対応しています。
| 運営会社 | INTLOOP株式会社 |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 20年以上の実績、38,000人以上の支援実績 |
| 公式サイト | high-performer.jp/career/ |
| 公開求人数 | 約1,420件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 業界知見豊富で、手厚いマンツーマン支援が受けられる |
| デメリット | 登録者が多く、対応に時間がかかる場合がある |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 中堅・ミドル層で確実なキャリアアップを狙う方 |
| 対象年齢 | 20代~40代 |
CDBエージェント
KICK ZA ISSUE株式会社が運営するCDBエージェントは、国内最大級のコンサルタントプラットフォーム「コンサルデータバンク」から派生したサービスです。ITコンサル案件に特に強く、未経験者でも積極的に転職支援を行います。非公開求人やプロジェクト案件が豊富で、最新のプラットフォームを活用して効率的なマッチングを実現しています。
| 運営会社 | KICK ZA ISSUE株式会社 |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 国内最大級のデータベース、ITコンサル案件に強い |
| 公式サイト | consul-data-bank.com |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 非公開求人やプロジェクト案件が豊富で転職成功率が高い |
| デメリット | サービス開始が新しく、戦略専業求人は少なめ |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | IT領域からの転身やITコンサルを目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~30代前半 |
MWH HR Products (MHRP)
MWH HR Products株式会社(※三井物産グループ)が運営するMHRPは、ハイクラス転職エージェントとして、コンサル・金融など幅広い業界の求人を扱います。20年以上の歴史を有する実績と、専属コンサルタントによる丁寧なサポートが強み。公開求人数は5,233件あり、転職後の年収アップ率も非常に高いです。
| 運営会社 | MWH HR Products株式会社(※三井物産グループ) |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス転職エージェント |
| 主な特徴 | 高年収求人が豊富、老舗並のノウハウ |
| 公式サイト | job.mwhhrp.com |
| 公開求人数 | 約5,233件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 高品質なサポートと独自求人、年収アップ実績が高い |
| デメリット | 新ブランドのため認知度が低く、求人は都市部中心 |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | ミドル~エグゼクティブ層で大幅なキャリアアップを目指す方 |
| 対象年齢 | 30代~50代 |
テックゲートエキスパート
株式会社セルバが運営するテックゲートエキスパートは、ITコンサル・エンジニア特化型転職エージェントです。特にITエンジニアからITコンサルタントへのキャリアチェンジ支援に力を入れており、年収1,000万円超の案件が豊富。オンラインで完結する手軽さが魅力ですが、戦略・経営コンサル志望者には求人が少ないため、IT領域を目指す方に最適です。
| 運営会社 | 株式会社セルバ |
|---|---|
| タイプ | ITコンサル・エンジニア特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | ITエンジニアからITコンサルへの転身支援、非公開求人が豊富 |
| 公式サイト | tecgate.selva-i.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開(約1,560件程度) |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | IT未経験者も積極支援、オンライン完結で手軽に利用可能 |
| デメリット | 戦略・経営コンサル求人は少なめ |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | ITエンジニア経験を活かしてITコンサルを目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~30代前半 |
コトラ (KOTORA)
株式会社コトラが運営するコトラは、金融・コンサル・経営管理などハイクラス特化型エージェントです。国内トップクラスの求人数(約28,685件)を誇り、金融が50%、コンサルが40%を占める求人割合が特徴。専門領域別の担当制を採用し、詳細な企業情報に基づくアドバイスが受けられます。金融・会計系コンサルに特化した求人が豊富で、専門性を重視する方におすすめです。
| 運営会社 | 株式会社コトラ |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス特化型エージェント |
| 主な特徴 | 金融50%、コンサル40%、専門領域別担当制 |
| 公式サイト | kotora.jp |
| 公開求人数 | 約28,685件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 豊富な求人と専門的なアドバイスが受けられる |
| デメリット | 専門特化型ゆえ他業界求人は少ない |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 金融・会計系コンサル志望の方 |
| 対象年齢 | 30代~50代 |
ASSIGN AGENT
株式会社アサインが運営するASSIGN AGENTは、若手ハイキャリア層に特化したハイクラス転職エージェントです。20代後半~30代前半を主な対象とし、未経験からもコンサル転職を目指す方に手厚いオンライン面談や面接指導を実施。専任のキャリアアドバイザーが個別にサポートし、転職成功に向けた戦略を提案します。
| 運営会社 | 株式会社アサイン |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス特化型(若手向け) |
| 主な特徴 | 20代後半~30代前半向け、未経験者も手厚い支援 |
| 公式サイト | assign-inc.com |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り(推定) |
| メリット | 若手向けに特化した丁寧なサポートが魅力 |
| デメリット | 40代以上や地方求人が少ない |
| 対応地域 | 全国(主に都市圏) |
| こんな人におすすめ | 若手ハイキャリア、未経験からコンサルを目指す方 |
| 対象年齢 | 約25~35歳 |
JAC Recruitment
株式会社JACリクルートメントは、ロンドン発の総合型転職エージェントです。約1,000名のコンサルタント陣が求職者と企業の両面を担当し、外資系やグローバル求人に強みがあります。公開求人数は21,549件あり、管理職クラスの求人が中心です。高年収案件とバイリンガル求人を求める方におすすめです。
| 運営会社 | 株式会社JACリクルートメント |
|---|---|
| タイプ | 総合型転職エージェント(ミドル・ハイクラス向け) |
| 主な特徴 | 両面担当制、外資・グローバル求人に強い |
| 公式サイト | jac-recruitment.jp |
| 公開求人数 | 約21,549件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 高年収求人とグローバル案件が豊富、両面担当で信頼性高い |
| デメリット | 求人レベルが高く、経験不足の場合は厳しい |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 即戦力として年収アップを狙う30~50代の方 |
| 対象年齢 | 30代~50代 |
doda X
パーソルキャリア株式会社が運営するdoda Xは、ハイクラス転職サービスで、スカウト型と求人応募型のハイブリッドです。年収800万円~2000万円級の非公開求人を多数抱え、約6.1万件の求人情報を提供。高待遇案件を求める方に最適ですが、現年収500~600万円以上が目安となるため、条件を満たす方向けです。
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス転職サービス(スカウト型+応募型) |
| 主な特徴 | 非公開求人多数、年収800万~2000万円級求人が充実 |
| 公式サイト | doda-x.jp |
| 公開求人数 | 非公開(約61,000件含む) |
| 担当のコンサル出身者有無 | 無し |
| メリット | 高待遇求人に効率的にアプローチでき、無料利用が可能 |
| デメリット | 現年収条件が厳しく、能動的な利用が必要 |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 高待遇求人を狙う30~40代の管理職層 |
| 対象年齢 | 30代~50代 |
リクルートダイレクトスカウト
株式会社リクルートが提供するリクルートダイレクトスカウトは、スカウト型転職サービスです。登録するだけで企業やヘッドハンターから直接オファーが届く仕組みで、リクルートのブランド力を背景に幅広い求人を提供。基本利用は無料ですが、職務経歴書の充実が必須です。
| 運営会社 | 株式会社リクルート |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス向けスカウト型転職サービス |
| 主な特徴 | 登録するだけでスカウトが届く、豊富な求人情報 |
| 公式サイト | directscout.recruit.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | なし |
| メリット | 簡単登録で多数のオファーが期待でき、利用料無料 |
| デメリット | 自己管理が必須で個別サポートが少ない |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 市場価値を試したい、受動的な転職活動を希望する方 |
| 対象年齢 | 全年代(実際は30~40代中心) |
エグゼクティブリンク
株式会社エグゼクティブリンクは、コンサル特化型転職エージェントです。BCG・マッキンゼー出身者による無料ケース面接講座や、書類・面接対策のサポートが充実。年間500名以上の内定実績を誇り、トップファーム志望の方におすすめです。
| 運営会社 | 株式会社エグゼクティブリンク |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 無料ケース面接講座、書類添削、面接対策が充実 |
| 公式サイト | executive-link.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 手厚い面接対策と高内定実績が魅力 |
| デメリット | 登録者が多く日程調整が煩雑、地方対応はオンラインのみ |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 戦略ファーム志望で徹底対策を求める方 |
| 対象年齢 | 20代~30代 |
アンテロープ (Antelope)
アンテロープキャリアコンサルティング株式会社が運営するアンテロープは、金融・コンサル特化型エージェントです。金融求人が半数を占め、特に財務・会計系コンサルに強みがあります。公開求人数は約4,537件で、非公開求人も充実。専門性を重視する方に適しています。
| 運営会社 | アンテロープキャリアコンサルティング株式会社 |
|---|---|
| タイプ | 金融・コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 金融50%、コンサル40%、独自診断ツールと長期フォロー |
| 公式サイト | antelope.co.jp |
| 公開求人数 | 約4,537件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 高専門性と好条件求人にアクセス可能 |
| デメリット | 他業界求人は扱わず、若手には案件が少なめ |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 金融・会計系コンサル志望者 |
| 対象年齢 | 30代~40代 |
クライス&カンパニー
株式会社クライス&カンパニーは、ハイクラス人材特化型ヘッドハンティングエージェントです。経営幹部クラスの求人を豊富に扱い、平均年収が高く、内定実績も優秀。主に首都圏を中心とした求人が対象で、管理職以上を目指す方に最適です。
| 運営会社 | 株式会社クライス&カンパニー |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス特化型ヘッドハンティングエージェント |
| 主な特徴 | 高年収求人、経営幹部求人に強い、両面担当制 |
| 公式サイト | kandc.com |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 高待遇求人と独自情報によるマッチングが優れている |
| デメリット | 経歴が不十分だと利用しにくい、首都圏中心 |
| 対応地域 | 主に首都圏 |
| こんな人におすすめ | 管理職以上でさらなるキャリアアップを狙う方 |
| 対象年齢 | 30代~50代 |
ランスタッド
ランスタッド株式会社は、世界最大級の総合型転職エージェントです。グローバルなネットワークと全国拠点を活かし、外資系・グローバル求人に強みがあります。コンサル経験者のポストコンサル転職にも定評があり、幅広い求人とサポートが魅力です。
| 運営会社 | ランスタッド株式会社 |
|---|---|
| タイプ | 総合型転職エージェント(グローバルに強み) |
| 主な特徴 | 全国・海外求人網が豊富、外資系に強い |
| 公式サイト | randstad.co.jp |
| 公開求人数 | 数千件規模(公開求人) |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | グローバルネットワークと幅広い求人が魅力 |
| デメリット | 専門的なケース対策は限定的、担当者にばらつきあり |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 外資系・グローバル転職を目指す方 |
| 対象年齢 | 20代後半~50代 |
FlowGroup (フローグループ)
株式会社Flow Groupが運営するFlowGroupは、コンサル特化型エージェントです。大手・外資系コンサル求人に特化し、全アドバイザーが大手出身である点が魅力。マンツーマンの手厚いサポートを重視しており、未経験者からでも戦略コンサル転職を実現できるよう支援します。
| 運営会社 | 株式会社Flow Group |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | 大手コンサル出身者によるマンツーマンサポート重視 |
| 公式サイト | consul-career.com |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 手厚い個別支援と高品質な求人情報が得られる |
| デメリット | 求人が東京・関西中心、対応地域が限定的 |
| 対応地域 | 全国(主に都市部) |
| こんな人におすすめ | 未経験から戦略コンサルを目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~30代 |
タイグロンパートナーズ
タイグロンパートナーズ株式会社は、金融・コンサル・CxO特化型エグゼクティブサーチです。ハイクラス求人(年収1000万円超)が主力で、各業界出身のプロが担当。若手向けの案件は少ないものの、管理職やエグゼクティブ層の転職を狙う方には非常に有力です。
| 運営会社 | 株式会社タイグロンパートナーズ |
|---|---|
| タイプ | ハイクラス特化型エグゼクティブサーチ |
| 主な特徴 | 年収1000万円超求人に強く、企業との直接パイプが厚い |
| 公式サイト | tiglon-partners.com |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | トップ層求人が豊富で、即戦力案件に直結 |
| デメリット | 若手向けは不向き、求人は首都圏中心 |
| 対応地域 | 主に東京 |
| こんな人におすすめ | 即戦力として更なるキャリアアップを狙う方 |
| 対象年齢 | 30代~40代 |
リネアコンサルティング
リネアコンサルティング株式会社は、2008年設立のコンサル特化型転職エージェントです。PwC出身の人事担当者などが在籍し、企業側の視点を重視した具体的なアドバイスが魅力。厳しい審査基準もあるため、真剣に転職活動に臨む方に向いています。
| 運営会社 | リネアコンサルティング株式会社 |
|---|---|
| タイプ | コンサル特化型転職エージェント |
| 主な特徴 | PwC出身担当者による企業視点の具体的アドバイス |
| 公式サイト | linea.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 具体的なフィードバックと企業情報に基づく支援が受けられる |
| デメリット | 審査基準が厳しく、登録が断られる場合がある |
| 対応地域 | 東京中心 |
| こんな人におすすめ | 本気でコンサル転職を目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~40代前半 |
キャリアインキュベーション
株式会社キャリアインキュベーションは、コンサル・PE・経営層特化型エージェントです。戦略コンサルからPEファンド、事業会社のCxOへの転職支援に強みがあり、専任コンサルタントがきめ細かくサポート。長期的なキャリア形成を重視し、経営者層とのネットワークも豊富です。
| 運営会社 | 株式会社キャリアインキュベーション |
|---|---|
| タイプ | コンサル・PE・経営層特化型エージェント |
| 主な特徴 | 戦略コンサルからCxO転職まで一気通貫のサポート |
| 公式サイト | careerinq.com |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 高い支援品質と長期的なキャリアフォローが魅力 |
| デメリット | 若手未経験者向け求人は少なめ |
| 対応地域 | 東京・大阪中心 |
| こんな人におすすめ | 戦略コンサルからCxOやPEファンド転職を目指す方 |
| 対象年齢 | 30代~40代 |
フォルトナ (FORTNA)
株式会社Fortnaが運営するフォルトナは、コンサル・経営幹部特化型ヘッドハンティングエージェントです。MBBやBIG4出身のヘッドハンターが在籍し、トップクラスのハイクラス求人に強みがあります。若手よりも即戦力経験者向けで、地方案件は限定的です。
| 運営会社 | 株式会社Fortna |
|---|---|
| タイプ | コンサル・経営幹部特化型ヘッドハンティング |
| 主な特徴 | MBB/BIG4出身のヘッドハンター在籍、CxO求人に強い |
| 公式サイト | fortna.co.jp |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | トップ層求人と企業ネットワークが充実 |
| デメリット | 若手・未経験向けは不向き、地方求人が少ない |
| 対応地域 | 東京中心 |
| こんな人におすすめ | 即戦力として上位ポジションを目指す方 |
| 対象年齢 | 30代後半~50代 |
ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社は、経営・財務領域特化型エージェントです。PEファンド関連の求人など独自の非公開求人が豊富で、業界未経験者でもチャレンジ可能な案件も扱っています。実績として年収増加率186%を公表し、信頼性の高いサポートが魅力です。
| 運営会社 | ヤマトヒューマンキャピタル株式会社 |
|---|---|
| タイプ | 経営・財務領域特化型エージェント |
| 主な特徴 | 独自の非公開求人が豊富、PE・VC関連に強い |
| 公式サイト | yamatohc.co.jp |
| 公開求人数 | 約2,903件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 高待遇求人と年収アップ実績が非常に高い |
| デメリット | 専門領域に特化しており、求人条件が限定される |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 経営・財務系コンサル、PEファンド志望者 |
| 対象年齢 | 20代~40代 |
パソナキャリア
株式会社パソナが運営するパソナキャリアは、総合型転職エージェントです。若手~ミドル層に幅広く対応しており、成長産業や注目企業への求人に強みがあります。特に女性の転職支援にも実績があり、幅広い求人と手厚いサポートが特徴です。
| 運営会社 | 株式会社パソナ |
|---|---|
| タイプ | 総合型転職エージェント |
| 主な特徴 | 幅広い求人網と女性支援に強み、若手~ミドル層対応 |
| 公式サイト | pasonacareer.jp |
| 公開求人数 | 約10,000件(公開求人ベース) |
| 担当のコンサル出身者有無 | 不明(専門チームあり) |
| メリット | 求人の幅広さと総合的サポートが魅力 |
| デメリット | コンサル特化対策はやや薄い可能性 |
| 対応地域 | 全国 |
| こんな人におすすめ | 成長企業や幅広い求人を比較検討したい方 |
| 対象年齢 | 20代~40代 |
LHH転職エージェント
デコ株式会社が運営するLHH転職エージェントは、総合型転職エージェントで、職種別の専門担当制を採用。360度式コンサルティングにより、グローバル求人や外資系求人に強く、各専門分野のスペシャリストが転職活動をサポートします。
| 運営会社 | アデコ株式会社 |
|---|---|
| タイプ | 総合型転職エージェント(専門職種担当制) |
| 主な特徴 | 360度式支援とグローバル求人に強い |
| 公式サイト | jp.lhh.com |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | 専門担当制で深い業界理解、グローバル案件が豊富 |
| デメリット | ケース面接対策は専門エージェントほどではない |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 専門スキルを活かし、グローバル転職を目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~50代 |
エンワールド
エンワールド・ジャパン株式会社は、外資系・グローバル企業特化型エージェントです。英語力を活かした求人やグローバルなネットワークが魅力で、海外案件やバイリンガル求人に強みがあります。長期的なキャリアパートナーとしても定評があり、特に外資系転職を目指す若手から中堅層におすすめです。
| 運営会社 | エンワールド・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| タイプ | 外資系・グローバル企業特化型エージェント |
| 主な特徴 | 外資系求人、英語を活かせる求人が充実 |
| 公式サイト | enworld.com |
| 公開求人数 | 約2,000件 |
| 担当のコンサル出身者有無 | 有り |
| メリット | グローバル求人の豊富さと長期支援が魅力 |
| デメリット | 首都圏・関西中心、英語求人が多い |
| 対応地域 | 全国・海外 |
| こんな人におすすめ | 英語力を活かしてグローバル転職を目指す方 |
| 対象年齢 | 20代~30代中心 |
転職エージェントを利用するメリット
戦略コンサルの転職において転職エージェントを活用をおすすめしています。
特に重要なメリットを詳しく解説していきます。
過去問情報や選考ノウハウを得られる
戦略コンサルならではの“過去問”の重要性
一般的な企業の面接と大きく異なる点として、戦略コンサルではケース面接やフェルミ推定がほぼ必須で行われることが挙げられます。これらの面接では、大まかな「考え方の型」こそあるものの、出題テーマや面接官の質問スタイルはファームごとに微妙に異なり、さらに評価のポイントも多岐にわたります。
そのため、「本番を想定した問題(過去問)」を事前に入手し、実際に練習を繰り返すことが内定への近道となります。しかし過去問は公開されていないケースが多く、個人ではなかなか手に入らないのが現状です。
エージェント独自の情報収集ルート
ここで大きな役割を果たすのが転職エージェントです。エージェントは日々、戦略コンサルファームへ応募した求職者の選考結果や面接内容をヒアリングしてデータ化しているため、独自に過去問や質問例を蓄積しています。
特に「コンコード」のような戦略コンサル特化型エージェントになると、大手町のオフィスに設けられたPCルームで過去問集を閲覧できるなど、他では得られないリアルな選考情報が手に入ることもあります。これは転職エージェントを活用する大きなメリットと言えるでしょう。またエージェントによっては過去受験した方の回答もみることができるため、内定にはどれくらいのレベル感が必要なのか把握することができます。
ケース面接対策の練習台となる企業を紹介
MBB本命前に“場数を踏む”重要性
マッキンゼーやBCG、ベインなどのトップファームを本命とする場合、いきなり本命企業の選考を受けるのはリスクが大きいです。戦略コンサルは一度不合格になると、再応募まで半年~1年あるいはそれ以上待たなければならないケースが珍しくありません。
そこで、志望度の高くない練習企業で実際の選考を通じて“場数”を踏み、自分のケアレスミスや弱点を把握することが重要になります。特にケース面接は、書籍や独学だけでは対応しきれない「その場での臨機応変なやり取り」や「面接官との空気感への慣れ」が大切なので、本番さながらの“練習試合”が役立ちます。
ブティックファームや総合コンサルを“ウォーミングアップ”に
転職エージェントは、その人の経歴や志向、スケジュールを踏まえたうえで、ブティックファームや総合系コンサルなどの面接を“練習台”として紹介してくれる場合があります。もちろんこれらの企業に本気で入社する意欲があるなら、そのまま第一志望にしても構いませんが、MBBを本命とするならウォーミングアップの選考を数社受けておくことで、面接の進め方や回答スタイルを実地で試すことができ、本番の成功確率がぐっと上がります。
企業研究が効率的に行える
公開情報だけでは見えない“生の情報”
戦略コンサルの世界は、企業ホームページで公開されている情報だけではプロジェクト内容やチーム編成、ファームのカルチャーなどがつかみにくいことが多いです。特に外資系戦略コンサルは守秘義務の関係で社内プロジェクトの事例を公表しにくく、一部抽象的なケーススタディのみを掲載していることが一般的です。
一方、転職エージェントは企業の人事担当者やコンサルタント自身と密なリレーションを築いており、
「実際どんな案件が多いのか」
「プロジェクトの忙しさや雰囲気はどうか」
「昇進スピードや評価基準は?」
といった内部事情を詳細に教えてくれます。こうした生の情報を得られるだけでも、キャリア選択の精度を格段に高められるでしょう。
長期的なキャリアパスの設計にも
さらに、エージェントによってはポストコンサルのキャリアに関する情報も得られます。戦略コンサルで数年働いた後、事業会社の経営企画やスタートアップにCFO・COOとして転身するといった実例や、MBA留学を経て海外拠点へスライドするパターンなど、具体的な進路をエージェントのネットワークから教えてもらうことが可能です。
「単に転職して終わり」ではなく、その先を見据えたキャリアプランを描くうえでも、エージェントの持つ情報は非常に有益です。
コンサル特化の選考対策
職務経歴書の添削や面接対策
戦略コンサル転職では、通常の一般企業の応募とは異なる観点でアピールポイントを整理する必要があります。職務経歴書では、成果を定量的に示すだけでなく、「現場課題をどのように構造化・解決したか」「リーダーシップをどう発揮したか」といったコンサルが重視する論理面の評価軸に沿った書き方が求められます。
コンサル業界の選考に強いエージェントには、コンサル出身のキャリアカウンセラーが在籍している場合が多く、応募書類をコンサル目線で添削してもらえます。また、ビヘイビア面接への対策なども、実務経験者だからこそポイントを押さえた具体的アドバイスを受けられるのです
面接対策をしてもらえる
面接対策においても、各社固有の特有の質問への対応練習やケース面接だけでなくビヘイビア面接についてもアドバイスをもらうことができます。
特にフェルミ推定の暗算スピードや、面接官からの突っ込みに対して落ち着いて論点を整理する練習は、リアルな模擬面接をこなさないと身につきにくいスキルです。こうした取り組みも、コンサル特化エージェントならではの強力なサポートと言えるでしょう。
※一方、エージェントの担当者によってばらつきがある&ケース面接対策に特化している仕事ではないためケース面接対策は実際に内定した人数人に壁打ちをしてもらったりケース面接対策講座を受講することをおすすめします。
採用動向がわかる
採用枠の増減やニーズの変化
戦略コンサル業界の採用は通年採用が中心ですが、ファームごとに景気やプロジェクト状況によって採用枠が増減することがあります。ある年度は未経験枠を積極的に募集していたのに、翌年度には経験者のみしか採っていないケースも少なくありません。
転職エージェントは常に企業の人事担当や現場コンサルタントと情報交換をしているため、リアルタイムの採用ニーズを把握しやすく、それに合わせた応募戦略を練ることができます。
転職エージェントとリファラル・直接応募の比較
転職する際は転職エージェントとリファラル・直接応募で迷う人が多いと思います。
それぞれの特徴と違いを詳しく見ていきましょう。
リファラル採用のメリット
書類選考で優位に立てる可能性が高い
リファラルは、すでにファームで働いている社員(推薦者)からの紹介という形になるため、企業側としては「既存社員がお墨付きを与える=ある程度安心できる」という心理が働きます。その結果、書類選考のハードルが下がりやすく、足切りに引っかかりにくい傾向があります。
一方、ある程度の学歴・経歴がある人であれば戦略コンサルの書類は中途であれば通りやすいためここはそれほど気にしなくてよいかもしれません。
テストや一部プロセスの免除がある場合も
リファラルで受験することで一般的な選考プロセスで課されるテストや適性検査が免除されるケースもあります。推薦者の紹介であれば最低限の地頭はあるだろうという前提のもと、面接から始まるケースが多いと考えています。
企業情報・カルチャー等が把握しやすい
リファラルをしてくれる知人や先輩社員から、リアルな社風・プロジェクト内容・昇進スピードなど、外部からは見えにくい情報を事前に聞き出せるメリットがあります。転職後のミスマッチを減らしやすいのは大きな利点です。
直接応募のメリット
企業側の予算がかからない
通常、転職エージェントを介した採用には企業側で紹介料(年収の何%)が発生します。直接応募であれば企業の費用負担が無いため、「予算が限られる中小ファーム」「採用コストに厳格な方針の企業」などでは、わずかに有利になる可能性があります。
ただし、外資戦略コンサルのような大手ファームでは予算が充分あり、費用削減の恩恵が採用判断に大きく影響することは比較的少ないと言えます。
企業との直接コミュニケーションが可能
エージェントを挟まない分、企業側と直接やり取りを行うため、伝達ミスやタイムラグを減らせる場合があります。日程調整や質問などをメールや電話で直接交渉できるので、自分が主体的に動きたい方には合っているかもしれません。
自分のペースで応募できる
転職エージェントはある程度のペースで「早めに他社も受けましょう」「この時期に出しましょう」と促してくる場合が多いです。直接応募なら自分の準備状況やタイミングに合わせて、慎重に書類提出や面接スケジュールを組むことが可能です。
これらのメリットを踏まえると、戦略コンサルへの転職では基本エージェント経由で進めていき、必要に応じてリファラルで進めていくことをお勧めします。直接応募についてはエージェントが扱っていない企業(Google, Microsoft等)を受ける際に利用することをお勧めします。
転職を成功させるためのエージェントの活用方法
希望条件を明確に伝える
エージェントに登録した直後のヒアリングでは、「希望する年収」「担当したい領域や案件」「ワークライフバランス」など、転職後の理想像をできるだけ詳しく伝えましょう。自分の希望や優先順位があいまいだと、エージェントからも最適な案件が紹介されにくくなります。
また、「戦略コンサルで3〜5年修行した後、事業会社に移りたい」「最終的には海外オフィスで活躍したい」など、長期的な視野を持っているなら、それもエージェントに伝えておくと良いです。ファームによっては海外派遣の制度やMBA支援があるので、キャリアビジョンに合致するファームを優先的に紹介してもらえます。
採用動向をヒアリングしスケジュールを相談
リアルタイムの採用トレンドを把握
戦略コンサルファームは通年採用が基本ですが、市況や案件数によって採用枠が増減することがあります。エージェントは企業の採用担当者や現場とのパイプを通じて、「今年は未経験採用が厳しめ」「デジタル部門の枠が大量に増えている」など最新のトレンドを把握しています。これに合わせて応募タイミングを調整することで合格率を高められます。
準備期間と“練習企業”の設定
フェルミ推定やケース面接は準備に時間がかかるため、自分の仕上がり具合に合わせてスケジュールを組むことが重要です。エージェントに「準備が整うまで応募を待ちたい」「志望度の低い企業で練習を積みたい」と伝えれば、最適な順序で選考を組んでくれるはずです。
過去問や選考傾向など情報をフル活用
戦略コンサルのケース面接では、面接官が過去に出題した問題を使い回すことが非常に多いです。そのため、エージェントが保有する“直近の受験者が遭遇した問題例”をチェックするだけでも、対策の精度が一気に上がります。
- 「どんな質問が出されたか」
- 「候補者はどんな回答をしたか」
- 「回答のどこに強くツッコミが入ったか」
これらの詳細を教えてもらえれば、具体的な対策を立てやすくなります。
コンコードは実際に受けた人の回答も見ることができますので、優秀な方の回答を参考にしながらケースを仕上げていくことをおすすめします。
模擬面接の依頼
戦略コンサルへの転職では、書籍や独学だけでは不十分です。実際の面接に近いかたちで練習し、思考プロセスを口頭で整理しながら回答するスキルを鍛える必要があります。
エージェントの中には、キャリアカウンセラーが元戦略コンサルタントだったり、特別なトレーニングプログラムを用意していたりするケースがあります。定期的に模擬面接を受けて、自分の弱点をフィードバックしてもらいましょう。
また、ビヘイビア面接も合否を大きく左右します。どんなにケース面接ができても、「この人と一緒に働きたい」「この人にリーダーシップがありそうだ」という印象を与えられなければ不合格になる可能性があります。
エージェントを使って、過去の面接事例や「志望動機をどうロジカルに語るべきか」「強み・弱みをどう整理するか」といった点も徹底的に確認しておきましょう。
選考中の結果連絡・日程調整の依頼
戦略コンサル転職では、複数のファームに同時期に応募して比較検討するのが一般的です。エージェントに依頼すれば、各社の日程調整や書類送付、選考結果のフォローなどを一括でやってもらえます。忙しいビジネスパーソンにとっては、大幅な時間短縮になります。
また、もし途中で不合格になったとしても、エージェントが企業に問い合わせることで「どの部分が足りなかったのか」「面接官の評価や改善点」を聞き出せる場合があります。個人応募では得られにくいフィードバックをエージェント経由で得ることで、次の受験に向けて早期に軌道修正できます。
オファー交渉を代理でしてもらう
戦略コンサルの報酬体系は企業ごとに幅があり、ポジションやグレードによって総額に大きな差があります。エージェントは各ファームの給与テーブルや交渉事例を熟知しているため、年収アップや有利な契約条件を引き出してくれる可能性が高いです。実際にオファー交渉をするだけで年収が数十万~数百万上がるケースは存在します。
求職者が直接企業に「あと○万円年収を上げてほしい」と交渉するのは心理的にハードルが高いですが、エージェントが間に入ればスムーズに進むことが多いです。企業側も、採用コストや市場相場を踏まえた上で妥協点を探るケースが一般的です。入社後の関係性に影響を残さずに条件交渉を完了できるのはエージェントを使う大きなメリットです。
転職エージェント利用の流れ
戦略コンサルへの転職を成功させるために、エージェント利用の具体的な流れを理解しておきましょう。
- Step1:エージェントへの登録
- Step2:キャリア面談の実施
- Step3:求人紹介
- Step4:選考対策・選考開始
- Step5:オファー・条件交渉
転職エージェントへの登録
まずは転職エージェントの公式サイトや登録フォームを通じて、希望職種や年収、職務経歴などの情報を入力し、自分のプロフィールを登録します。戦略コンサルを志望していること、現在のスキルや実績、リーダーシップ経験などもできる限り詳細に書き込むと、キャリアカウンセラーとの最初の面談がスムーズに進みます。
書類としては履歴書と職務経歴書をあらかじめ作成しておきましょう。
キャリア面談の実施
登録が完了すると、エージェントのキャリアカウンセラーとの初回面談が設定されます。対面かオンラインかはエージェントや個人の都合によって異なりますが、ここで「なぜ戦略コンサルなのか」「現職とのギャップ」「キャリアビジョン」などを明確にする作業が行われます。特に戦略コンサル特有のケース面接対策やフェルミ推定への意識、現時点での準備度合いを共有しておくと、今後の対策計画がスムーズに立てられます。
また、希望の年収や役職レベル、転職可能な時期や勤務地などの基本条件のすり合わせもこのタイミングで行われます。ここでしっかりと希望を伝えておかないと、後の求人紹介でミスマッチが発生することもあるため、優先順位を含めて遠慮なく相談しておくことが大切です。
求人の紹介
面談の内容を踏まえ、エージェントから具体的なコンサルファームの求人情報が提示されます。マッキンゼーやBCG、ベインなどの外資系戦略コンサルだけでなく、日系戦略ファーム、総合系コンサルの戦略部門、さらにはブティック系コンサルなど、幅広い選択肢を一度に比較できるのが大きなメリットです。各ファームが求めるスキルや人物像、社内の昇進スピード、プロジェクトの特徴など、公開情報だけでは得にくい“裏情報”を提供してもらえる可能性もあります。気になる求人があれば、職務経歴書をブラッシュアップし、エージェント経由で書類選考に進む形です。
面接対策・選考開始
書類選考が通過すると、面接段階に入ります。戦略コンサルの面接はフェルミ推定やケース面接など独特な形式が多いため、エージェントに模擬面接や過去問情報の提供を依頼すると効果的です。実際に合格者がどんな回答をしたのか、面接官がどんな観点で評価しているのかといった具体的な事例を聞き出せるかがポイントです。
面接の日程調整や連絡はエージェントが代行してくれるので、仕事が忙しい方でもスケジュール管理が楽になります。また、不合格だった場合の理由や面接官の感想などをフィードバックしてもらい、次の選考に向けて修正を図ることもできるのが大きな利点です。
オファー・条件交渉
面接を無事クリアすれば、企業からオファーレター(内定通知)が提示されます。戦略コンサルは年収レンジが幅広く、プロジェクトや役職、採用レベルによっても報酬が異なるため、エージェントを通じて年収やポジション、入社時期などの条件を交渉できるのは心強いポイントです。
もし複数のファームから内定を得た場合は、各社のカルチャーや強み、昇進スピードなどを改めてエージェントに確認し、自分のキャリアビジョンに最も合致する企業を選ぶことができます。その後、正式にオファーを受諾すれば入社準備に入り、現在の勤務先との退職交渉や書類手続きを進める形となります。エージェントはこうした最終フェーズの手続きやスケジュール調整についてもサポートし、スムーズに転職が完了するよう伴走してくれます。
エージェント利用で注意すべきこと
戦略コンサルの転職でエージェントを使う際に注意すべきことがあります。
早すぎる応募を避ける
戦略コンサルは一度不合格になると再応募まで半年〜1年あけなければならないケースが多く、他業界よりリスクが高いのが特徴です。しかし、エージェント側は早く実績を上げたい思惑があるため、「今すぐ応募しましょう」と急かしてくることがあります。ケース面接対策やフェルミ推定の練習が十分にできていない段階で本命企業に特攻してしまうと、取り返しのつかない結果になる可能性が高いので、応募のタイミングは自分の仕上がり具合を最優先してください。
本命の前に練習用企業を受ける戦略
ケース面接やフェルミ推定には独特の対話形式の練習が不可欠です。いきなりマッキンゼーやBCGのようなトップファームを受けて失敗すると、再応募が難しくなるため、まずはブティックファームや総合系コンサルなどで場数を踏む方法も有効です。エージェントには「まずは練習のために志望度の低い企業から受けたい」という意図を明確に伝え、スケジュールを調整してもらうようにしましょう。
キャリアカウンセラーとの相性を見極める
エージェント企業そのものの評判が高くても、担当キャリアカウンセラーのコンサル業界に対する理解度やネットワーク、指導力は人によって大きく異なります。とりわけ戦略コンサルは選考フローや面接内容に特殊な部分が多いため、担当者にその知識と経験がない場合、的外れなアドバイスで時間をロスすることになりかねません。
ペースの主導権を握る
エージェントが提案してくるスケジュールや「さまざまな企業を同時に受けましょう」というプランが、自分の事情に合わないこともあります。仕事が忙しい中で多くの面接を並行するのが難しい、あるいはケース面接対策にまだ時間が必要といった場合は、遠慮せずペースを調整してください。エージェントはあくまで支援者であり、あなたの転職活動を成功させるために存在しています。スケジュールや応募方針を含めて、自分の都合や準備状況を最優先して交渉することが、後悔のない転職を実現するコツです。
自身のペースでケース面接対策を進めていき、かなり仕上がってきたなと思ったタイミングで志望度が低い順に受け進めていくことをおすすめします!
戦略コンサル業界の転職でよくある質問
最後に、転職検討者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
未経験からコンサル転職は可能ですか?
未経験から戦略コンサルを目指すことは可能ですが、近年は採用基準が厳しくなっているのも事実です。エージェントに採用動向を確認しながら、必要であれば他業種やITコンサルでの経験を積むなど回り道を検討するのも一つの方法です。
30代後半からの戦略コンサルへの転職は難しいでしょうか?
30代後半でも戦略コンサルに転職する例は実際にたくさん存在します。
ポジションや期待される役割は若手と異なり、より高いマネジメント経験や業界知見が求められます。具体的には、これまでの職務経験を通じて培った専門性(金融や製造業など特定業界の深い知識やマネジメント経験など)が評価されやすいと考えられます。エージェントと相談しながら自分の強みをどうアピールするか戦略を立てるとよいでしょう。
戦略コンサルとデジタルの戦略との違いは?
戦略コンサルのデジタル部門は経営課題をデジタルの観点で解決していくことにあります。AIやクラウドを活用した業務改革、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略の策定など、従来の戦略コンサル業務にITやデータサイエンスの視点を組み合わせて行うことが特徴です。
一般的な戦略コンサル部門と比較すると、テクノロジーの知見やデータ分析スキルが強く求められるため、ITコンサルやSIerの上流工程経験がある人材も積極的に採用している傾向があります。経営課題の解決と同時に技術実装面での具体的な提案が必要になる点が大きく異なります。
グローバル案件に携わりたいのですが、英語力はどの程度必要でしょうか?
外資戦略コンサルが多いこともあり、英語でのコミュニケーションを要する案件は多く存在します。ただし、必要とされる英語力は企業やプロジェクト次第で特別にTOEICなどのスコアが必須とは限りません。重要なのは、英語での会議に参加し、議論をリードできるかどうかという実務的コミュニケーション能力です。
英語ができない場合でも海外案件やグローバル企業をクライアントにする場合は、メールや電話会議だけでなく、プレゼン資料も英語で作成することがあります。日常的に英語を使っていない方でも、入社後に本格的な語学トレーニングを受ける例もあるため、事前にエージェントへ企業ごとの英語要件を確認しつつ、自分のレベルアップ計画を立てておくのがおすすめです。
ケース面接の対策はどのくらい時間をかければ良いですか?
フェルミ推定やケース面接で求められる思考力は、短期間で一夜漬けのように身につくものではありません。多くの受験者は少なくとも2〜3カ月、場合によっては半年以上かけて徹底的に練習します。毎日1問ずつフェルミ推定を解く、ビジネスケースのフレームワークを暗記する、友人やエージェントの模擬面接に参加するなど、反復練習が重要です。とりわけMBBクラスのファームだと、面接官が追加質問やツッコミを入れることが多いため、論点の優先度付けやコミュニケーション力、短時間の暗算力など総合的なスキルを磨く必要があります。エージェントから過去問情報や面接官の癖などを聞き出しながら、実践的な対策を積み重ねると合格可能性が大幅に上がるでしょう。
こちらの記事も参考にしてみてください。

3カ月の徹底攻略で戦略コンサルに内定したいならStrategy Academyがおすすめ
ケース面接対策は独学でもできますが、時間がかかる上に実際に合格レベルにいるかどうかを自分で確認することは実際難しいと考えています。
仕上がっていない段階で受けてしまい全落ちしてしまう方がほとんどです。
もし「MBBをはじめとする戦略コンサルに挑戦してみたい」「ケース面接対策に不安がある」と思っている方は実際に面接を通過した経験のある人にマンツーマンで見てもらうことで正しいやり方を学び内定レベルのアウトプットと自分の距離感を理解することが重要です。
Strategy Academyでは、MBB出身コンサルタントのマンツーマンレッスンにより内定まで伴走支援をします。
- 独実テキストにより内定直結する内容を効率的に学べる事
- MBB出身コンサルタントのマンツーマンレッスンが受けられること
- 実際に合格レベルにあるかどうかを判定してもらえること
Strategy Academyでは3カ月の徹底攻略で戦略コンサル内定レベルのケース面接力を手に入れることができます。
対策していく中で分からない点や不安な点があればチャットでいつでも解決することができます。
「戦略コンサルティングファームに内定したい」と本気で思っている方はStrategy Academyを是非活用してみてください